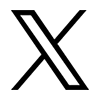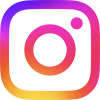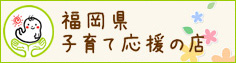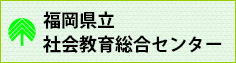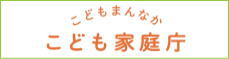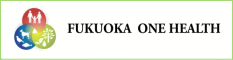令和7年3月18日
おさらい:非認知能力は学力テストで測定できる認知能力とは異なり、自分をコントロールする力、ストレスと上手に付き合う力、協力して取り組む力、レジリエンス(回復力・柔軟性)、チャレンジする姿勢、忍耐力、共感力など数値では測れない力を指します。
これらの力を育てるための大切な要素として、これまでに「愛着形成」や「レジリエンス」について取り上げてきましたが、今回はもうひとつの大切な要素「自分と他者を大切にする心」を育てることについて取り上げます。
自分と他者を大切にする心は、他者との交互に学びあう環境の中で育まれると考えます。そのため、対話的な学びや経験がとても重要です。
対話とは
単なる会話や意見交換ではなく、お互いの価値観を尊重する姿勢を基盤として、お互いの気持ちを伝えあい、その意味を深めながら一緒に新たな理解を創造していくプロセスを指します。
お互いを評価したり主張ばかりするのではなく、そして正解や結論を急ぐのでもなく、相手の言葉に耳を傾け、お互いの理解を深めること。そして、異なる価値観が共存できる場を創造していくことが重要です。
学校や教育環境でも、グループワークやプロジェクト学習など協働的な学びの重要性が見直されており、自己他者理解を深めるためのワークショップや、地域との対話を通したキャリア教育など様々な取組が実践されています。わたしたち大人は、子ども達の想いや言葉をしっかり聴いて、適時フィードバック(応答)をしたり、失敗しても学べるという安心な場を作りながら、子ども達がわくわくと主体的に学ぶ機会や環境を支えていけたらいいですね。
そんな他者との対話を通した協働的学びの中で、新しいアイデアや自分一人では思いつかなかった視点を交流すること、それぞれの意見が大切にされることで、お互いを理解し信頼する経験を通し、自分も他者も大切にする心を育んでいける社会になって欲しいと願っています。