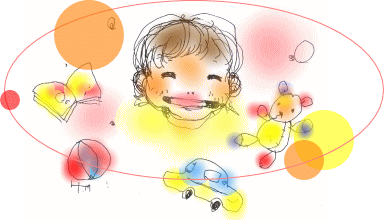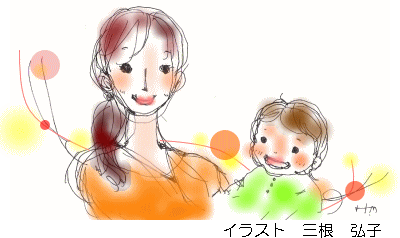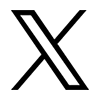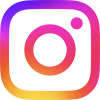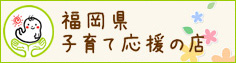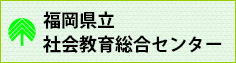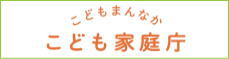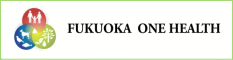~母乳育児・離乳の支援~第1回 母乳育児のメリットについて考えてみましょう。≪母乳、評価再び≫
平成19年10月30日
赤ちゃんが生まれたら出来るだけ母乳を与えましょう。母乳育児が今再び見直されています。そこで、今回は是非みなさんに母子の健康をはかるうえでも母乳育児のメリットをよく知っていただきたいと思います。また、多くの出産施設では母乳育児の支援の一つとして「赤ちゃんが欲しがる時はいつでも母乳をあげられるように母児同室」を行なっています。退院後も当分の間あきらめずに「泣いたら吸わせる」を繰り返してみましょう。
母乳育児のメリット
≪母子間のつよいきずなができます≫
赤ちゃんにとって、直接母親との肌と肌のふれあいは、母子間のつよいきずなができます。
ゆったりとした気持ちで、楽しみながら母乳をあげてください。
≪栄養学的に母乳は最適です≫
母乳は、消化・吸収の面からも最高の贈り物です。さらに、免疫物質を豊富に含んでいるために、病気に対する抵抗力を高め病気にかかりにくくなります。
≪あごや脳の発達によい影響を与えます≫
母乳を飲むためには、赤ちゃんのあごや舌をじょうずに使わないと母乳が飲めません。この母乳を吸う運動は、あごや脳に刺激を与え、赤ちゃんにとってよい影響を与えます。
≪その他≫
・ 卵巣腫瘍や乳がんにかかりにくいといわれています。
・ 乳幼児突然症候群にもかかりにくいといわれています。
このように、母乳育児は母親にとっても、赤ちゃんにとってもすばらしいものなのです。
しかし、母乳を授乳できないお母さんもいます。このような場合、大事なのは愛情、赤ちゃんをしっかり抱っこし目を見つめながらミルクを与えるようにしましょう。坂井 邦子

 前回は、母乳育児のメリットについてお話しました。今回は母乳育児を与え続けるために、お母さんが毎日取っている食事についてお話します。乳児期の子どもをもつお母さんは、食事について気をつけておられることと思います。
前回は、母乳育児のメリットについてお話しました。今回は母乳育児を与え続けるために、お母さんが毎日取っている食事についてお話します。乳児期の子どもをもつお母さんは、食事について気をつけておられることと思います。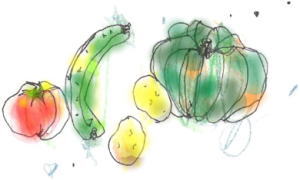
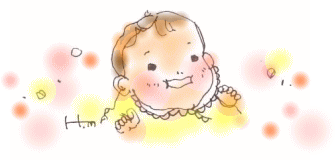 産後お母さんにとっては、生まれたばかりの赤ちゃんにどのように接してよいか分からず戸惑うことも多いと思います。その戸惑いのひとつに、母乳育児の相談も多く寄せられています。母乳育児が赤ちゃんにとって最良の栄養だと分かっても、赤ちゃんがいつも美味しく飲んでくれるとはかぎりません。赤ちゃんが泣いたら、まずオムツを替えてあげましょう。そのときは、声かけをしながらお尻や足を優しくなでてあげるのもいいでしょう。生後0~3ヶ月の赤ちゃんは、時間を気にせず赤ちゃんが欲しがるときに、母乳を与えましょう。お母さんは、ゆったりした気持ちで母乳を与えましょう。授乳後は、必ずゲップをさせてから寝かせましょう。今回は母乳育児中に多く寄せられる相談についてお話します。
産後お母さんにとっては、生まれたばかりの赤ちゃんにどのように接してよいか分からず戸惑うことも多いと思います。その戸惑いのひとつに、母乳育児の相談も多く寄せられています。母乳育児が赤ちゃんにとって最良の栄養だと分かっても、赤ちゃんがいつも美味しく飲んでくれるとはかぎりません。赤ちゃんが泣いたら、まずオムツを替えてあげましょう。そのときは、声かけをしながらお尻や足を優しくなでてあげるのもいいでしょう。生後0~3ヶ月の赤ちゃんは、時間を気にせず赤ちゃんが欲しがるときに、母乳を与えましょう。お母さんは、ゆったりした気持ちで母乳を与えましょう。授乳後は、必ずゲップをさせてから寝かせましょう。今回は母乳育児中に多く寄せられる相談についてお話します。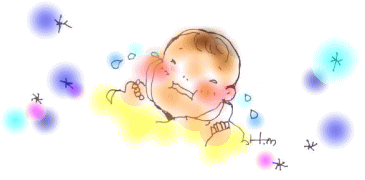 お乳が張りすぎるときは、少し水分をとるのを控えめにしましょう。また、あまり張りすぎるときは、母乳を与えた後、母乳を搾り出すのもひとつ方法です。また、乳頭に亀裂が見られる場合は、乳頭保護器を使用するか直接授乳する時間を短め(片方3分程度)とし、後は搾ったお乳を与えるようにしましょう。
お乳が張りすぎるときは、少し水分をとるのを控えめにしましょう。また、あまり張りすぎるときは、母乳を与えた後、母乳を搾り出すのもひとつ方法です。また、乳頭に亀裂が見られる場合は、乳頭保護器を使用するか直接授乳する時間を短め(片方3分程度)とし、後は搾ったお乳を与えるようにしましょう。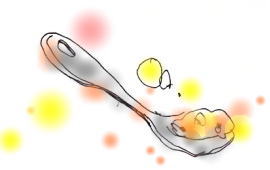 生後5か月頃の赤ちゃんは、母乳またはミルク等の乳汁栄養のみでは、栄養素が不足しがちになります。特に、鉄・カルシュウムやビタミンC・D等が不足しがちです。この頃になると、首のすわりがしっかりし、支えてやるとお座りができるようになり、食べ物にも興味を示し、スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなってきます。また、この時期には、よだれが多く見られるようになってきますが、よだれが出るのは、赤ちゃんの消化・吸収が発達した証拠であり、そろそろ離乳を始める目安となります。そこで、今回は離乳の支援ポイントについてお話します。
生後5か月頃の赤ちゃんは、母乳またはミルク等の乳汁栄養のみでは、栄養素が不足しがちになります。特に、鉄・カルシュウムやビタミンC・D等が不足しがちです。この頃になると、首のすわりがしっかりし、支えてやるとお座りができるようになり、食べ物にも興味を示し、スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなってきます。また、この時期には、よだれが多く見られるようになってきますが、よだれが出るのは、赤ちゃんの消化・吸収が発達した証拠であり、そろそろ離乳を始める目安となります。そこで、今回は離乳の支援ポイントについてお話します。 ?離乳を開始して1か月を過ぎた頃から、離乳食は1日2回にしていきます。母乳またはミルクは離乳食の後に与えましょう。生後7,8か月頃からは舌でつぶせる固さのものを与えましょう。2回食の頃には、たんぱく質(卵黄,肉,魚)のものを取り入れてみましょう。
?離乳を開始して1か月を過ぎた頃から、離乳食は1日2回にしていきます。母乳またはミルクは離乳食の後に与えましょう。生後7,8か月頃からは舌でつぶせる固さのものを与えましょう。2回食の頃には、たんぱく質(卵黄,肉,魚)のものを取り入れてみましょう。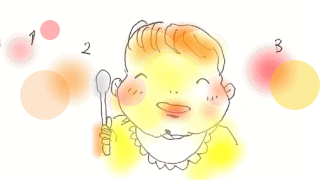 離乳は、1日1回1さじずつから開始し、子どもの様子を見ながら無理のない方法で進めていきましょう。離乳が進むにつれて、1日2回食、3回食へと食事のリズムをつけ、生活リズムを整えていくようにするとよいでしょう。子どもにとって、食べる楽しさの体験を増やしていくようにしたいですね。
離乳は、1日1回1さじずつから開始し、子どもの様子を見ながら無理のない方法で進めていきましょう。離乳が進むにつれて、1日2回食、3回食へと食事のリズムをつけ、生活リズムを整えていくようにするとよいでしょう。子どもにとって、食べる楽しさの体験を増やしていくようにしたいですね。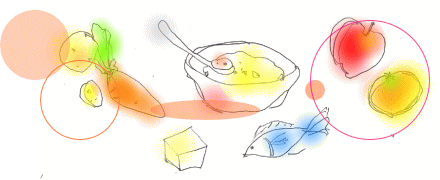 このほか、離乳の進行に応じてベビーフードを利用するのもよいです。赤ちゃんは細菌の抵抗力が弱いので、調理を行なう際には、衛生面に十分に注意したいものですね。調味料はできるだけ使用せずに、食品のもつ味を生かしながら、薄味で調理するようにしましよう。
このほか、離乳の進行に応じてベビーフードを利用するのもよいです。赤ちゃんは細菌の抵抗力が弱いので、調理を行なう際には、衛生面に十分に注意したいものですね。調味料はできるだけ使用せずに、食品のもつ味を生かしながら、薄味で調理するようにしましよう。