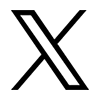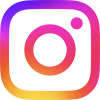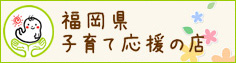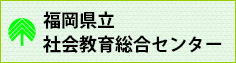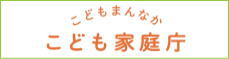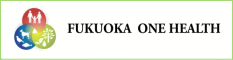~人間関係を豊かに~第1回・・・子どものこころに寄り添って・・・
平成19年5月9日

幼稚園は遊具やおもちゃが沢山あって、しかも同年齢の子どもたちがいて、概ね楽しいところです。でもそのせいで幼稚園の中ではいざこざがよく起こります。その時子どもはおかあさんの手助けがなくそれを乗り越えなければなりません。でもこのいざこざが当事者は勿論、周りの子どもたちの心を豊かにしていくのです。
たとえば・・・
たまたま同じ場所で楽しくブロック遊びをしていたA男とB男。A男は飛行機、B男はロボットをつくっています。A男はいきなりB男からブロックを取り上げ自分の飛行機にくっつけました。B男はびっくりしてA男からブロックを取り返そうとしましたが、A男はなかなか返しません。ついにB男はA男を叩きA男は泣き出してしまいました。大人はすぐに、きっかけを作ったA男に「先に取ったでしょ!だめじゃない」と言ってしまうでしょう。
でも、A男もB男も自己主張をしたのです。幼稚園では先ず「自分のものにしたかったのね」「痛かったのね」「悔しかったのね」とそれぞれの気持ちを言葉にして共感をします。子どもはそのことで「気持ちをわかってくれた」と心を和ませ、心を開きます。そして自分がブロックを取られたら、自分が叩かれたらどんな気持ちがするのか考えることができるようになります。そして相手の気持ちに気づいて来るのです。先生や友だちから支えられ、先生や友だちの温かさに気づいていきます。そして周りの子どももその出来事の成り行きをじっと見ていて学ぶのです。

おかあさんは『幼稚園の中では悲しい思いはして欲しくない』と思うものです。お子さんが「ちっとも面白くない、もう幼稚園には行きたくない」と言って幼稚園から帰ってこられる日もあるでしょう。おかあさんはそのお子さんの気持ちに共感しながらも『今、心が育っている途中なんだ』と広い心と温かい愛情を持ってお子さんのすべてを受け止めてあげてくださいね。きっと翌日は元気になって、いざこざがあった子どもと仲良く遊べると思いますよ。(篠栗町立勢門幼稚園主任 原田 幸子 先生)



 今、子どもたちの遊びの中で人気があるのが、どろだんご作りです。一言にどろだんごと言っても奥が深いんですよ。
今、子どもたちの遊びの中で人気があるのが、どろだんご作りです。一言にどろだんごと言っても奥が深いんですよ。 
 子どもたちは、園内の太鼓橋の下の土を使えば、上手く作れるということを前の大きい組の遊びを見て知っています。年長組が橋の下に集まってだんご作りを始めると、年少組が遠巻きに見ています。それを見た年長組が、『作っちゃろうか?』と言って小さなだんごを作ってくれると、それをもとに自分で「さらさら土」をかけてだんごらしきものができあがります。この橋の下で、年少と年長の交流が見られます。
子どもたちは、園内の太鼓橋の下の土を使えば、上手く作れるということを前の大きい組の遊びを見て知っています。年長組が橋の下に集まってだんご作りを始めると、年少組が遠巻きに見ています。それを見た年長組が、『作っちゃろうか?』と言って小さなだんごを作ってくれると、それをもとに自分で「さらさら土」をかけてだんごらしきものができあがります。この橋の下で、年少と年長の交流が見られます。



 職場体験では、中学生が子どもたちと一緒に遊んだり、おんぶや抱っこをしてくれたり、ボール遊びを教えてくれたりします。<たった3日間程度の関わりですが、道であったりすると、「あっ、中学校のおにいちゃんだ。」と声をかけたり、「きのう、中学校のお姉ちゃんにあったよ」と幼稚園で嬉しそうに話してくれます。
職場体験では、中学生が子どもたちと一緒に遊んだり、おんぶや抱っこをしてくれたり、ボール遊びを教えてくれたりします。<たった3日間程度の関わりですが、道であったりすると、「あっ、中学校のおにいちゃんだ。」と声をかけたり、「きのう、中学校のお姉ちゃんにあったよ」と幼稚園で嬉しそうに話してくれます。


 なかなか解決がつかないので「I君が困っているのでちょっとだけ見せてね」と、保育者がS男のロッカーから作品を取り出しました。数点の同じ様な作品が出てくると「それ僕が作ったと」と主張するI男、すかさず「これ僕の」とS男、「僕が作ったと」I男、お互いの主張の繰り返しでいつまでも平行線です。
なかなか解決がつかないので「I君が困っているのでちょっとだけ見せてね」と、保育者がS男のロッカーから作品を取り出しました。数点の同じ様な作品が出てくると「それ僕が作ったと」と主張するI男、すかさず「これ僕の」とS男、「僕が作ったと」I男、お互いの主張の繰り返しでいつまでも平行線です。 子どもは、思いをぶつけあい、自分の思いを受け止められることによって心に余裕が生まれ、相手の気持ちを受け止めることができるようになり、それを繰り返しながら人とのかかわり方を学んでいきます。なによりもこの経験の積み重ねが大事です。日々の雑事に追われて忙しいでしょうが、子どもの話をよく聞き、まず子どもの気持ちを丁寧に受け止めることですね。大人が善悪を決めつけたり方向性を示唆したりせず・・・。心に余裕がないとできないですね。よく話を聴いてもらった子どもは人の話もよく聴こうとするんですよ。(篠栗町立北勢門幼稚園 阿倍 正子 先生)
子どもは、思いをぶつけあい、自分の思いを受け止められることによって心に余裕が生まれ、相手の気持ちを受け止めることができるようになり、それを繰り返しながら人とのかかわり方を学んでいきます。なによりもこの経験の積み重ねが大事です。日々の雑事に追われて忙しいでしょうが、子どもの話をよく聞き、まず子どもの気持ちを丁寧に受け止めることですね。大人が善悪を決めつけたり方向性を示唆したりせず・・・。心に余裕がないとできないですね。よく話を聴いてもらった子どもは人の話もよく聴こうとするんですよ。(篠栗町立北勢門幼稚園 阿倍 正子 先生)