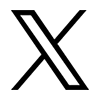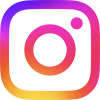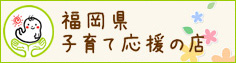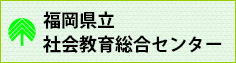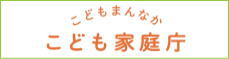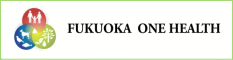令和7年7月28日
前回はLGBTQ+の子ども・ユースにとって、家族からの否定や拒絶がメンタルヘルスに重大な影響を及ぼすこと、家族からの受容が重要であることを書きました。
この場合の家族からの否定や拒絶とは以下のようなものを指します。
・子どもがLGBTQ+であることを予防しようとしたり変えさせたりしようする
・「子どもがLGBTQ+であることは恥ずかしいことだ」とか、「そうであることにがっかりしている」などと子どもに言う
・LGBTQ+であることに対して身体的な罰や精神的な罰を与える
まだまだLGBTQ+への誤解や偏見がはびこる今の社会では、我が子がLGBTQ+のどれか、いくつかである、あるいはそうかもしれないと知った時、否定的、拒絶的な感情や考えが自分の中で湧き上がることはあるかもしれません。しかし、もしその感情や考えをお子さんに言葉や態度などで伝えてしまうと、お子さんを深く傷つけてしまう可能性が高いため注意が必要です。
では、子どもの性のあり方に対して否定的、拒絶的な感情や考えが自分の中で湧き上がった時に、どうしていけばいいのか。今回はその方法をいくつか紹介していきます。
♢ジャーナリングする
ジャーナリングとは、一定の時間内に頭に浮かんでくる考え、感情、イメージなどを紙に書いていくことです。言葉や文章で書くだけでなく、絵でもいいですし、言葉にも絵にもならないものを紙にペンをはわせて描く線で表現するのも十分に効果があると言われています。
我が子の性のあり方を知った後、混乱したり動揺や不安などの様々な感情が沸き起こって心や頭が忙しいけれど、実際に誰かに相談しようという気持ちになれないことは、そのような状況であればごく自然なことです。ジャーナリングであれば、紙と筆記具があれば誰にも気兼ねすることなく自分の感じていることや考えをありのままに表現することができます。
♢自分と向き合う
もし自分の中に否定的、拒絶的な感情や考えがあることに気がついた場合、どうしてそれが起こっているのか、何が根底にあるのか、自分と向き合ってみることで、それをほぐしたり乗り越えたりしていく糸口が見つかることもあるかもしれません。
♢性の多様性について知る
LGBTQ+について、あまりよく知らないことが否定的、拒絶的な感情や考えの根にある場合は、性の多様性について知っていくことで、誤解や偏見をほぐしていくことができます。
最近はLGBTQ+に関する書籍も色々あるので、自分に合う一冊を見つけてみることをおすすめします。
<様々な人のことを知ることのできるウェブサイト>
様々なLGBTQ+の人たちのストーリーに触れることも、否定的、拒絶的な感情や考えをほぐしていくのに役立つことがあります。
・PALETTALK
・LGBTER
<トランスジェンダーや多様な性別のことを知ることのできるウェブサイト>
・性別違和のあるお子さんと家族のための情報サイト
・trans101.jp はじめてのトランスジェンダー
トランスジェンダーについてネット上には様々な情報があふれています。特に最近はトランスジェンダーに対してネガティブに発信された情報も多くあり、トランスジェンダーやそうかもしれないお子さんをもつ家族にとって、お子さんの今後がとても心配になるような情報を見てしまうこともあるかもしれません。
そのような場合には、上記の「trans101.jp はじめてのトランスジェンダー」というウェブサイトがおすすめです。SNSのトランスジェンダーに関する情報のファクトチェックやおすすめの動画コンテンツなども掲載されています。
♢相談する
誰かに相談することは、苦しい気持ちを和らげたり、気持ちや状況を整理したりすることの助けになるかもしれません。ただ、もし身近な人に相談しようとする場合はアウティングにならないように気をつけなければいけません。
アウティングとは性的指向、恋愛の指向、性自認、出生時につけられた性別、性別移行に関すること、HIV/エイズのステータスなどを本人の同意なく第三者に暴露することです。
もしご自身の身近な人に相談しようとする場合は、それがアウティングになってしまわないよう、事前にお子さん本人にその人に相談してもよいかを聞き、お子さんの意向を尊重することが大切です。
♢LGBTQ+に関する専門の相談窓口に相談したい場合
もし専門家に相談したい場合は、認定NPO法人ReBitが情報をまとめているこちらのページに各地の相談窓口や交流会に関する情報も掲載されているので参考になると思います。
・先生のためのLGBTQに関するオンライン情報センター
♢サポート団体とつながる
LGBTQ+の子どもをもつ家族をサポートする団体があるので、それらの団体とつながることで得られるものは多いのではないかと思います。
<LGBTQ+の子どもをもつ家族をサポートする団体>
・NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会
・にじっこ
LGBTQ+の子どもをもつ家族をサポートする活動に特化している団体はまだ多くなく、自分の地域にはないという場合もあるかもしれません。認定NPO法人ReBitが情報をまとめているページに各地の団体や交流会等のことも紹介されているので、下記URLよりぜひご参照ください。
・先生のためのLGBTQに関するオンライン情報センター(相談先を探す)
♢最後に
最初の記事でお伝えしたことを最後に改めて伝えさせてください。
今の日本の社会はLGBTQ+の人たちにとって生きやすいものとは言えません。自分の子どもがLGBTQ+のどれか、いくつかかもしれないという時、我が子は幸せに生きていけるのかと不安に思うかもしれません。
しかし、生きにくい社会だからこそ身近な家族から性のあり方も含めてまるごとの自分らしさを受容され、必要な時にサポートを受けながら子ども時代を過ごせることは、生きづらい社会を生き抜いていく根源的な力を育むことにつながります。年齢に関わらず人の性のあり方は変化していくこともありますが、都合よく変化させられるというものではありません。
たとえ今すぐに受容することはできなかったとしても、性の多様性について学びながら少しずつ感覚をほぐしていってみませんか?
※この記事で紹介されているリンクは、執筆者個人の推薦に基づくものであり、ふくおか子育てパークがその内容を推奨したり、保証したりするものではありません。