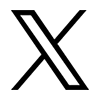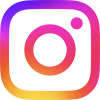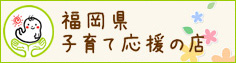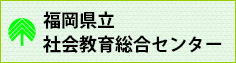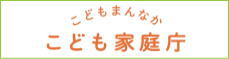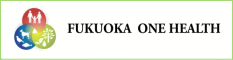1.知っておきたい!子どもの自立の第一歩~安心の土台づくり~
令和7年8月26日
「アタッチメント」という言葉を聞いたことはありますか?直訳すると「ピタッとくっつく」という意味です。心理学では赤ちゃんと特定の大人との間に育まれる、深い信頼の絆のことを指します。実はこのアタッチメントが、子どもの心の安定や、後の学び・人間関係の土台になっていくのです。
では、赤ちゃんはどうして「ピタッとくっつく」のでしょう。その人が好きだから?…実は、そうではありません。赤ちゃんは不安や怖さを感じたときに、近くの大人にピタッとくっつきます。これが本能的なアタッチメントです。くっつく相手やくっつき方は成長とともに変化していきます。
このように、アタッチメントは自分の心身を守るための行動なので「子どもが助けを求めたときに応える」ことがとても大切です。「知らない場所に来た」「知らない人がいる」「ママが少し離れた」…そんなときに、子どもが不安そうにひっついてきたら、まずはギュッと受け止めてあげてください。「初めての場所だね」「ちょっと怖かったね」などの声かけがあると安心感につながります。
こうして「困ったときには頼っていい」「自分は守られている」という感覚が育つと、子どもは少しずつ自分で安心を感じられるようになり、やがて自分から離れていく=自立の第一歩を踏み出します。
子育ての大きな役割は、子どもが心身ともに自立していくためのサポートです。そのためには、アタッチメントという“安心の土台”が欠かせないのです。これから4回に渡りアタッチメントの魅力をお伝えしますね。